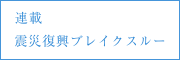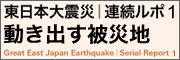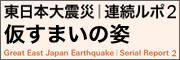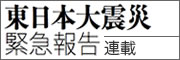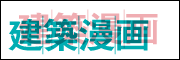『建築雑誌』は、明治20年から続く日本最古の建築メディアです。
本文PDFの閲覧につきましては、こちらでご確認ください。
本文PDFの閲覧につきましては、こちらでご確認ください。
2026-1
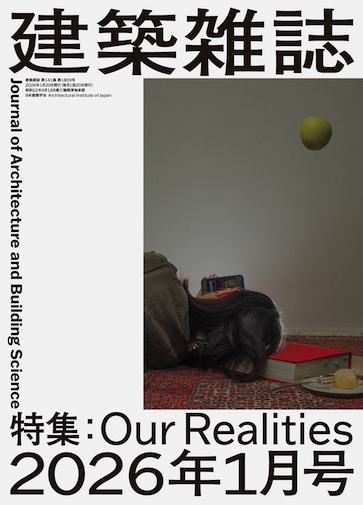
2026-1月号 JANUARY
特集= 01 Our Realities
01 Our Realities
特集01 Our Realities
「Our Realities」とは、リアリティを単一の現実として捉えるのではなく、複数の現実が並行して存在することを示している[*]。自らの実感に根ざした現実、遠い誰かにとっての現実、別の生物が生きる現実、フェイクとして立ち上がる現実、あり得るかもしれない現実、地球規模の現実、足元の裏庭に広がる現実─。
単一の未来像を描くことがいっそう困難になった現代において、こうした複数形のリアリティを見据えることは、不確定性を可能性へと転換するための視座ともなり得る。
建築から世界を一方向的に見わたすのではなく、世界に広がるさまざまな現実から建築を見返す視点をもつことで、その先に多様な可能性が立ち現れることを期待している。
今号では、今後の特集を担う編集委員の方々に、それぞれが向き合う現実やそこでの実感、そしてその先に見え隠れする建築の行方について述べていただいた。
[*]複数形の「Realities」という概念については、スペキュラティブ・デザイン分野のFionna Raby氏とAnthony Dunne氏が述べており、今回のテーマを掲げるうえでも参照している。
| [目次] |
| 00 | 巻頭連載 100人×100字のリアリティーズ |
| 02 | 年頭所感 環境構築の専門家として、人口減少社会に対峙する 小野田泰明 |
| 04 | 特集 Our Realities |
| 05 | 論考1 多様な現実の輪郭を辿る10年 小林恵吾 |
| 07 | 論考2 学生と向き合う、架空のリアリティーズ 伊藤維 |
| 09 | 論考3 オルタナティブな世界からみるデザイン 井本佐保里 |
| 11 | 論考4 千載の分岐点におけるリアリティーズ キャズ・T・ヨネダ |
| 13 | 論考5 タイムスケールをめぐる三題 加藤悠希 |
| 15 | 論考6 修理可能な世界に向けて 川勝真一 |
| 17 | 論考7 読替えと組換えの構造デザイン 福島佳浩 |
| 19 | 論考8 精度を超えてリアリティへ 富樫英介 |
| 21 | 論考9 暮らしのなかのコモニング 宮原真美子 |
| 23 | 論考10 見えない眼鏡─建築を語ること、研究すること 連勇太朗 |
| 25 | 論考11 建築をめぐる循環のかたち 山田宮土理 |
| 27 | 論考12 変化のリアリティ/リアリティの変化 中村航 |
| 29 | 特集 100人×100字─私たちの現実が映し出す風景 |
復興のリアリティーズ:01
| 40 | 「解体」のリアリティ 武内優 |
海外建築家による現代へのまなざし:01
| 42 | レム・コールハース氏 インタビューその① レム・コールハース |
ものづくりの過去と現代:01
| 44 | 「歩留まり」について 伊藤維 |
ノードとしての建築展:イントロダクション
| 45 | 建築史のエフェメラな背景 川勝真一 |
越境の現場を巡る─:01
| 46 | 包摂・ケア・共生の最前線 宮原真美子 |
| 47 | お知らせ 『建築雑誌』電子化について 会誌編集委員会 |
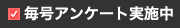
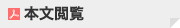
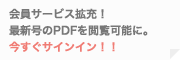
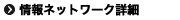
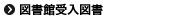

 『幸せな名建築たち 住む人・支える人に学ぶ42のつきあい方』
『幸せな名建築たち 住む人・支える人に学ぶ42のつきあい方』